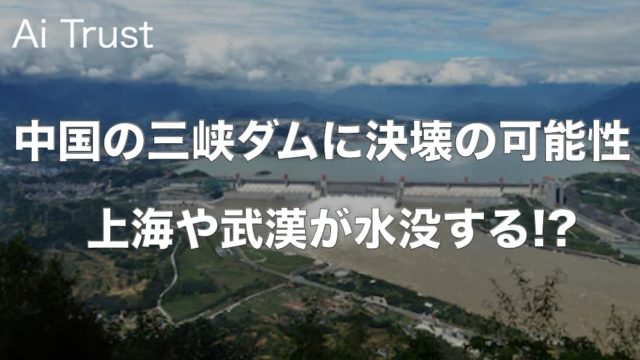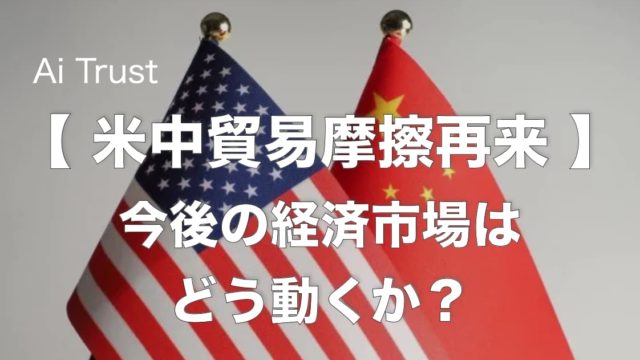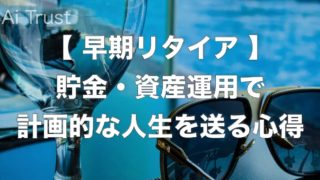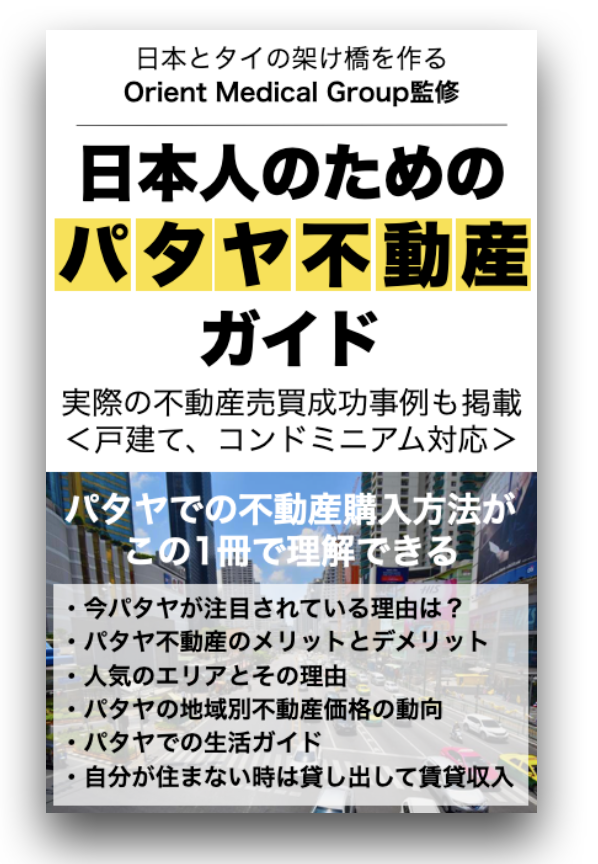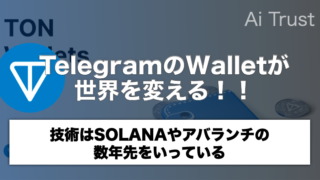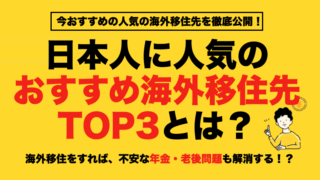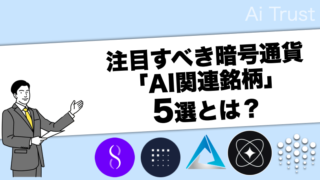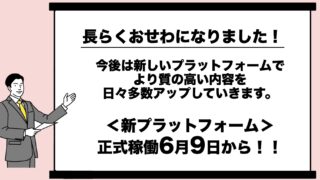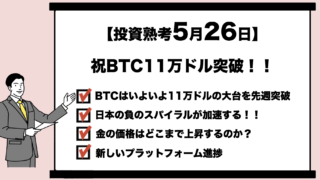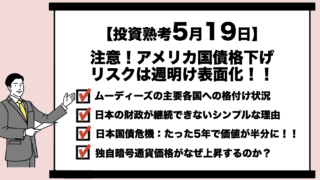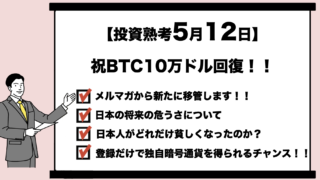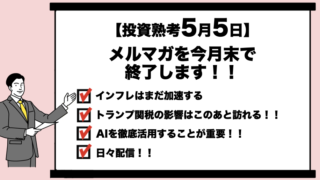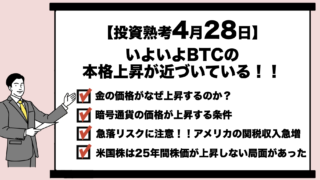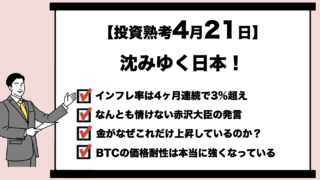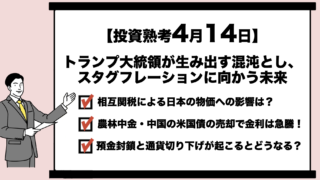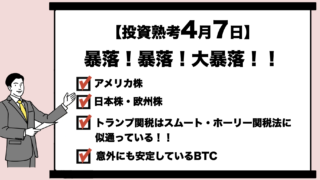ソフトバンクグループの株価は軟調
ソフトバンクGの株価は8月初旬の7,000円弱の水準から、先週半ばの安値は5,451円まで20%以上の調整を見せました。3月19日の2,687円からの急激な株価の上昇も、大規模な自社株買いにより、信用売りを行う投資家達を資金力により潰し、買い戻させたことで加速化されました。
金融資本市場を理解し尽くした孫正義氏ならではの方法とも言え、今回の米TEC株でのオプション取引も自社株買いでの成功があったからこその行動だったとも言えるのではないでしょうか。今日は上場企業の社会性と利益追求姿勢について焦点を当てて話を進めていきましょう。
様々な議論を呼ぶソフトバンクグループのオプション取引
ソフトバンクグループのオプション取引については様々な議論を呼んでいます。そもそも社内のコンプライアンスの体制そのものに大きな問題もあったようで、既に統括責任者は退任しています。グループ・コンプライアンス・オフィサー(コンプライアンス最高責任者)チャド・フェントレス氏が既に退職していますが、フェントレス氏は、ソフトバンクGなどが10兆円規模の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を設立した翌年の2018年に同社に入社しました。
ビジョン・ファンドは、真価が未知数のウィーワークのような新興企業に桁外れの投資を行い、非公開企業のバリュエーション(評価)をつり上げたと批判を浴びました。ビジョン・ファンドはその後上場テクノロジー企業に投資する戦略に転じましたが、ハイテク株のバブルを思わせる高騰を警戒する投資家がその動きを注視しています。
そしてソフトバンクGを最近数週間で辞めた幹部は、フェントレス氏だけではありません。米フォード・モーターからロビイストとして引き抜いたジアド・オジャクリ氏も退職する意向を先月明らかにしていますし、ここにきて幹部の相次ぐ離脱は今回のオプション取引の問題の根深さを感じさせられます。
孫正義商店
今回の米TEC株でのオプション取引は、想像するに、利益が出る確率がかなり高いことが明確だったため、孫正義氏が社内でゴリ押しする形で進めたのだと思われます。
そして、そもそもそうであれば、ソフトバンクGという上場企業を絡めず、孫正義氏が個人のリスクでこの取引でやれば良い話だと誰もが思うはずです。しかしそうしなかった理由としては、ソフトバンクGの手元資金を使えば、より大きな商いができ、より大きな商いを行うことで、より大きな利益を上げることにつながります。
そしてその結果的としてソフトバンクG株の株価の上昇につながり、自らの持つ株式の価値も上昇しますし、配当を大きく取ることでの税制メリットもありますので、ソフトバンクGで行ったのではないかと考えられるわけです。
しかし、今のところの結論から言えば、今回の取引自体に多くの投資家は疑問を感じ、株価が急上昇していたこともあり、利確を行う機会となり、行為につながったわけなのです。
ソフトバンクGはデリバティブで構築した数十億ドル規模のポジションについて、マイクロソフトやフェイスブックなど少数の優良テクノロジー企業に対象を絞ってきたと投資家に対して強調しています。
高いレバレッジをかけた短期の取引ではなく、コールスプレッドなどだったと説明していますが、詳細はまだ明らかになっていません。株価が下落したことで、ソフトバンクGの孫正義社長はこうした戦略を続けるかどうかを再考しているようですが、どのような戦略変更が行われ得るかはまだ明らかになってはいません。
利潤を追うことだけが企業として正しい行為なのか?
証券会社や銀行が自己資金での売買で同じ投資を行ったとしても、リスクはどうなのか?という点は言われたとしても、金融市場で利益を追求する行為にたいして、とやかく言われるようなことはないのでしょう。
今回のソフトバンクGの場合、事業会社であるからこそ、此処まで様々議論されるわけですが、事業会社の中でも当然、投資による収益を求める部署を持つところは多数あるわけで、商社などその最たるものです。
なぜバフェット氏はソフトバンクGに投資をしないのか?
ウォーレン・バフォット氏はバークシャー・ハサウェイ社を通じ、今回日本の5大商社株をそれぞれ5%程度ずつ購入しました。そして今後も最大10%程度までは買い増す予定もあると言っています。しかし商社よりも時価総額の大きな、ソフトバンクG株についてはバークシャー・ハサウェイ社、バフェット氏は購入していません。
バフェット氏の投資戦略は明確で、自らが理解できる株式を購入すると常に言っていますが、バフェット氏にしてみても、ソフトバンクG株については、同じ投資会社でもあるはずなのに、事業そのものが分かりにくく、孫正義氏の手法について、” 本物だとは思っていない、理解できない ” からだと言えるのかもしれません。
孫正義氏の方法が、邪道とまでは言いませんが、あまりにもイレギュラーなことを繰り返すことで、分かりにくくリスクも高いと感じているのかもしれません。
これは既存投資家からしても同様であり、不明瞭な行為、投資手法は会社への信頼を失うことにつながり、株は売られることになるわけです。しかしそこで価格が安くなれば、割安感も出てきますので、株式投資を行う投資家からすれば、大きなチャンスにもなり得るわけです。
株式投資は人の心理、駆け引きの綱の引き合いでもあり、企業としての姿勢とは度外視された土俵での戦いでもあるわけなのです。
投資についての考え方も人それぞれ
利益だけを追求する投資もひとつの方法です。そしてそれぞれの企業の経営者の理念、会社の行動に投資をするのもひとつの方法です。お金に色はないというのも間違いありませんし、これが金融資本主義です。金融資本主義の原理を理解し活用すれば、企業は富を大きく増やすこともできますし、その企業に投資を行う投資家はその分前を株価の上昇という形で得ることができます。
ゼロ金利、マイナス金利が継続的に続く中、新型コロナが収束に近づけば、低金利を活用した自社株買いも今後は進んでいくことになるでしょう。自社株買いが進めば株式の流動性が狭められますので、結果的に株価の上昇につながります。
株価が上昇すれば、経営陣は高い報酬を得ることができますので、お金へのモラルハザードは、現在の金融資本経済が続く限り、繰り返されるわけなのです。
過剰流動性相場、アフターコロナバブルへの戦略は?
世界中の株式市場は、過剰流動性資金によって、企業業績とはかけ離れた形で上昇が続いています。しかしこれは何処かのタイミングで必ずショック安が来ます。
基軸通貨のドルに円から分散させること。そして長期的な視点から成長株をドルコスト平均法で分散投資を行うこと。これが今最も正しい投資戦略となります。
“ WBL ウォーレン・バフェット・ロング “
バークシャー・ハサウェイ社よりも更に割安に市場で買うノウハウが詰まっています!!今すぐこちらからご確認ください。
毎週1回情報をまとめてお送りします。

AI TRUSTでは日々の金融市場に影響を与えるニュースを独自の視点から解説を行っています。是非ご自身の投資指標としてご活用ください!!