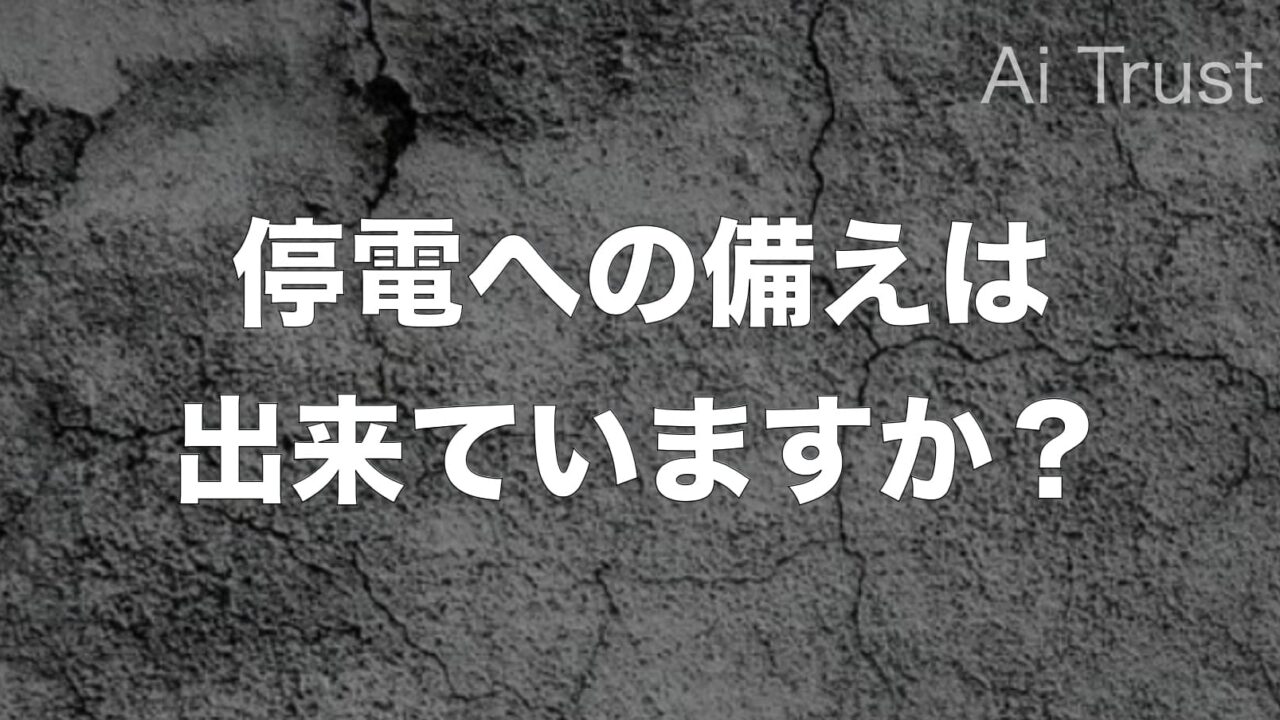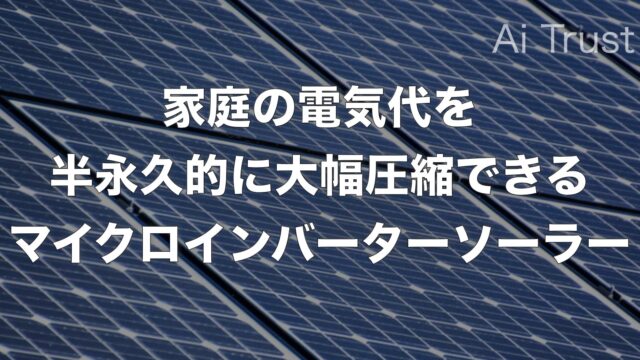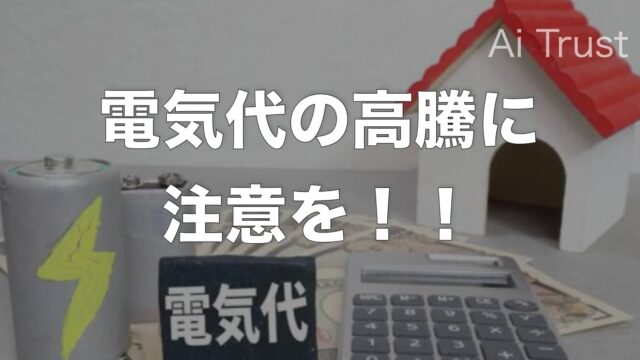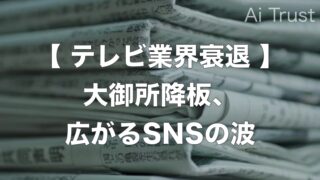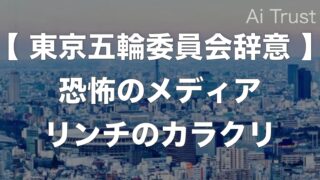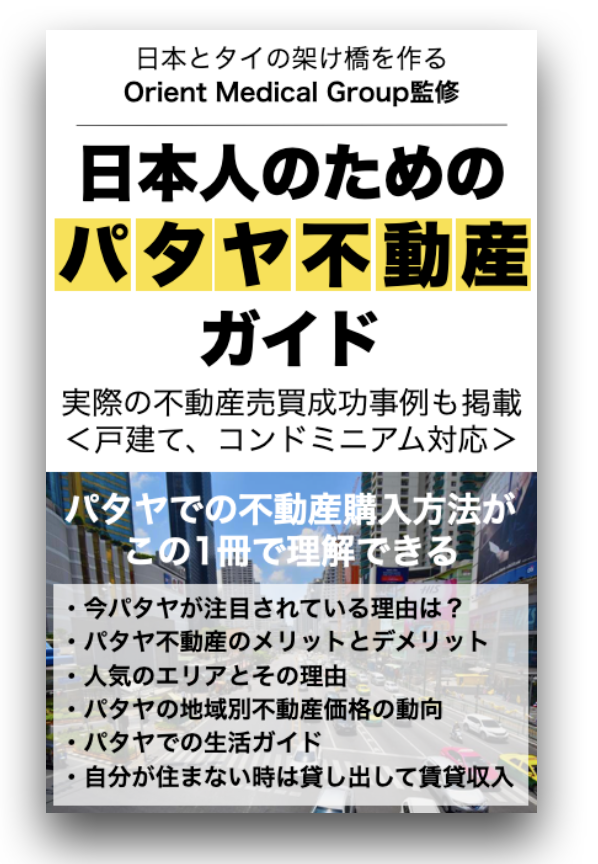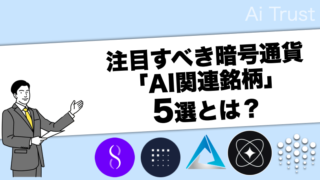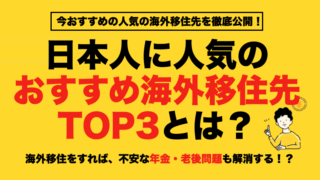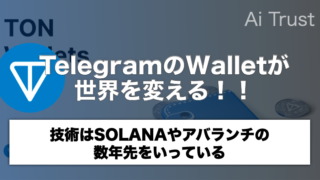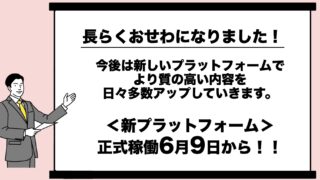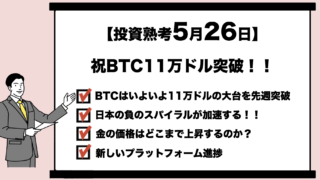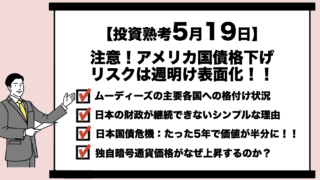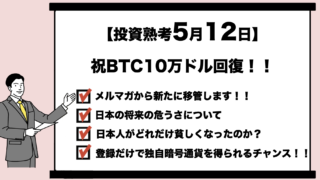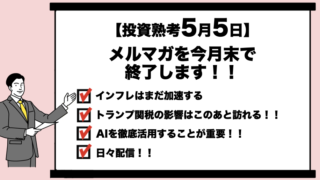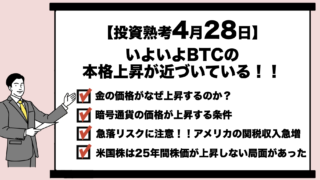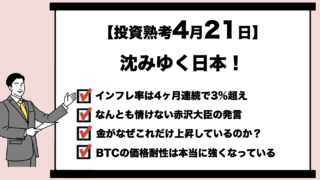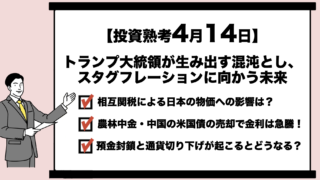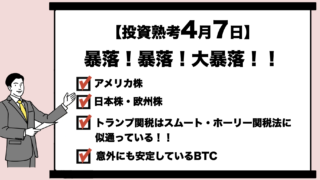2月13日午後11時8分ごろ、福島県沖を震源とするマグニチュード(M)7.3の地震があり、最大震度6強を観測した。震源の深さは約60キロ。気象庁によると、2011年3月の東日本大震災の余震と考えられています。
長く続いた地震は10年前の東日本大震災を思わせるには十分だった揺れであり、長さでした。
NHKによると、これまでのところ福島県や宮城県、関東地方で計100人以上が負傷し、
東北・関東地方では一時、約92万戸が停電したとのことです。
2月の夜の温度は零度以下の東北・関東地方ですがその中での停電は暖房器具がストップして、かなりの寒さとなりました。
布団に入っている人が多い時間帯だったとはいえ、災害時の暗闇はとても不安であり、寒さはとても厳しいものです。
この機会にぜひ防災の備えを見直しましょう。
まず何より確保しておきたいのは電気です。
明かりとしての確保もそうですが、最低限の電化製品を動かせる電力を確保しておくことが大切です。
一般的な消費電力
普段使用している家電や身の回りの電化製品の消費電力を把握しておくことが防災への第一歩です。
そもそも消費電力とは、その電化製品を動かすのにどれだけの電力を必要とするのか(消費するのか)でワット(W)という単位が使われます。ちなみに1000W(ワット)は1kW(キロワット)になります。
電化製品には消費電力を表示することが義務付けられていますので、必ずあるので確認してみましょう。
※下記は概算で機種やメーカーなどによって異なります。
一般的なもの
スマートフォン 18w
ノートパソコン 45w
電気毛布 40w
TV 80w
ファンヒーター 燃焼時30w
炊飯器 100~300w
冷蔵庫 100~300w
消費電力が高めなもの
電子レンジ 1,000~1,400w
電気ポッド 900~1400w
ドライヤー 600~1,200w
エアコン 500~3,000w
消費電力を知っておくと確保している電気がどのくらい使えるかがわかるので非常に便利です。
さらにもう一つ知っておきたいのがWhです。ワットアワーと読みますが、1時間使用できる電力のことです。
最低限の確保しておきたいお手頃な、常備しておきたいものは500whほどのバッテリー(蓄電池)ですが、これを例にすると
スマートフォンがおよそ18wなのでこの場合、500÷18となるので、およそ27回充電できる計算になります。
電気毛布だったら40wなので、およそ12時間くらい使用できることになります。
このような計算になりますので、普段使用する電化製品が災害時にどのくらい使えるか把握できることになりますね!
例えばファンヒーターだったら点火時の瞬間消費は300wになりますが、その後の燃焼時は30w程度なので500Whぐらいのポータブルバッテリーがあれば十分に賄えます。
逆に消費電力が高めのものは使うことが出来ません。電子レンジやドライヤーなど瞬間的に大きな電力を消費するものは業務用のような大きめのバッテリーが必要になります。
この辺りがわかっていると使用することが出来るもの、消費電力が高めで使えないものもわかってくるので、災害用の備えとしては消費電力が低めのもので準備しておくと良いでしょう。
合わせてポータブルのソーラーパネルもあると充電も可能となるのでさらに万全です。

今後の地震の可能性は?
気象庁の発表によると余震はまだ続き今後10年はあるとされています。
さらに政府の地震調査委員会が発表している南海トラフで想定されるマグニチュード8から9の巨大地震については、今後30年以内に発生する確率は80%となっており、いつ起きてもおかしくないとされているのです。
これらを考えると、日本はいつ地震が起きてもおかしくない状況にありますので、万全に備えることでぜひそのリスクを下げるようにしましょう。
毎週1回情報をまとめてお送りします。

AI TRUSTでは日々の金融市場に影響を与えるニュースを独自の視点から解説を行っています。是非ご自身の投資指標としてご活用ください!!