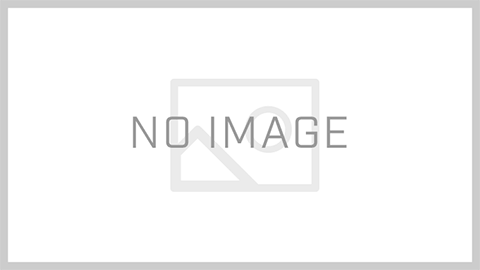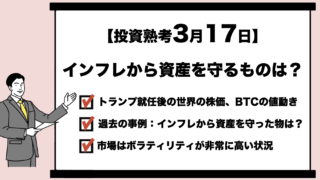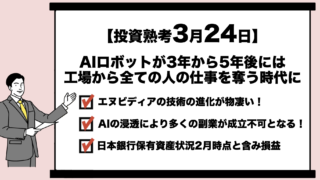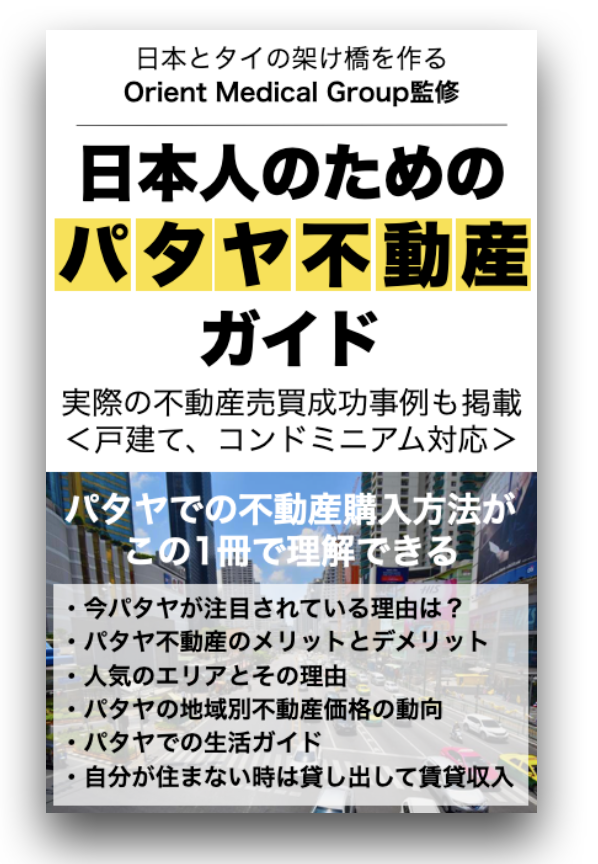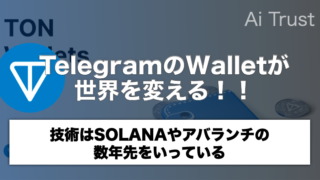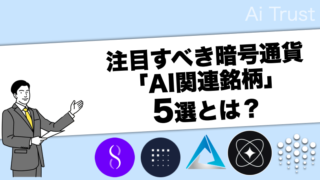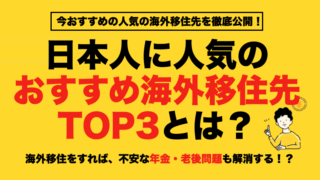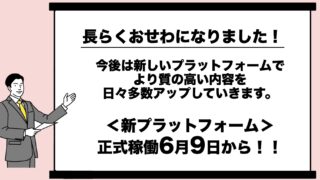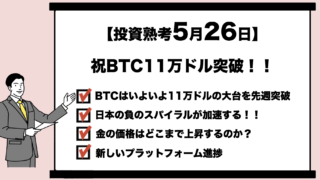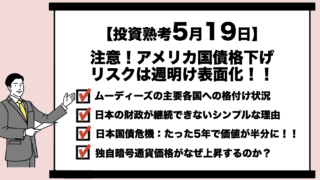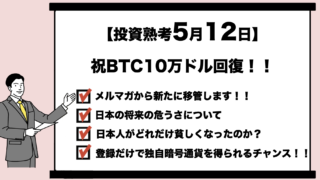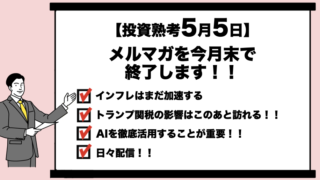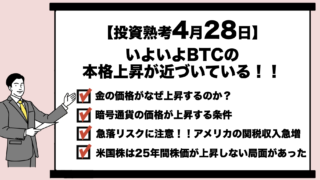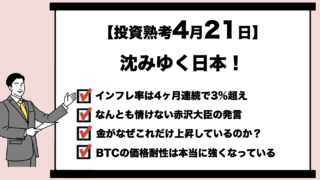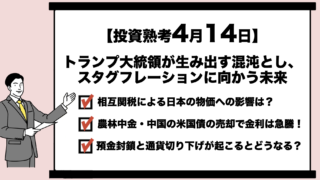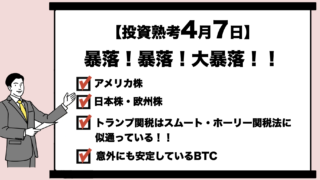[読み上げ音声再生]
日本銀行の保有資産状況(2025年2月時点)と含み損益
日銀の国債・株式・ETF保有状況と含み損益
国債(日本国債):
日本銀行は大規模な金融緩和の結果、巨額の国債を保有しています。2024年3月末時点で日銀の国債保有残高は簿価で約589.6兆円に達し、その時価評価額は約580.2兆円でした。この差額約9.4兆円が含み損に相当し、2023年3月末の約0.2兆円から急増しています。その後、金融緩和の縮小や利上げに伴う長期金利上昇で国債価格が下落したため、含み損はさらに拡大しました。2024年9月末時点では含み損が過去最大の約13.66兆円に達しています。この時点で10年国債利回りは約0.8%台半ばまで上昇しており、日銀の自己資本(約12.7兆円)の約8割に相当する損失が潜在的に生じている計算です。ただし日銀は満期保有を前提とした簿価会計(償却原価法)を採用しているため、時価の変動による評価損は決算上ただちに表面化しません。植田総裁も「含み損が膨らんでも政策運営に支障はない」と説明していますが、含み損の巨額化は市場に日銀財務への不安を招きかねない状況です。
ETF(上場投資信託):
日銀は金融緩和の一環で株式ETFも大量に買い入れてきました。簿価合計は約37兆円に上り、これらの時価評価額は2024年1月末時点で約67兆円と推計されています。したがって含み益は約30兆円にも達し、日銀保有ETFだけで東証株式時価総額の約7%を占める規模です。この巨額の含み益は、売却して実現すれば国庫納付金として政府財政に貢献し得る一方、市場への売却は株価下落を招くため「絵に描いた餅」とも評されています。日銀は現時点でETF売却の方針は示しておらず、「含み益は相当ある」としつつも慎重に検討する姿勢です。株式(個別株)については、日銀はかつて銀行保有株の買取りを行った実績があります。2002~2004年にかけて累計約2.018兆円の銀行保有株を取得しており、現在も一部を保有しています。この株式ポートフォリオも株価上昇により評価益が生じているとみられますが、規模はETFに比べれば小額です。総じて、2025年2月時点の日銀は国債で数十兆円規模の含み損を抱える一方、ETF等のリスク資産で数十兆円の含み益を有していると考えられ、バランスシート上では表面化していないものの大きな評価損益を内包する状態です。
金利急騰シナリオの影響シミュレーション
今後、仮に金利が急上昇し長期金利が2%、3%、4%と上昇した場合、日銀のバランスシートおよび政府の財政に深刻な影響が及ぶと想定されます。以下では(1)日銀バランスシートと(2)政府財政の2点について、シナリオ別に概算の影響を示します。
(1) 日銀バランスシートへの影響:評価損の拡大
金利上昇により国債価格が下落すると、日銀保有国債の含み損は一段と拡大します。長期金利が約2%まで上昇するシナリオでは、現在0%近辺で保有している国債群の価格が大幅に低下し、含み損はおよそ55兆円規模に膨らむと試算されます(簿価589兆円に対し時価約534兆円程度)。これは日銀の自己資本(約13兆円)を遥かに上回り、日銀は含みベースで数十兆円の債務超過状態となります。同様に金利3%まで上昇した場合、含み損は約85~90兆円規模に達し得ます。さらに4%に達すると含み損は100兆円を超え、日銀の自己資本とETF含み益(約30兆円)をすべて相殺してなお巨額の累積損失が残る計算です。実際、民間試算でも「長期金利が1%上昇すると日銀は約29兆円の債務超過、2%上昇で約56兆円の債務超過に陥る」と指摘されています。もっとも日銀が国債を満期まで保有すれば帳簿上は損失を実現しないため、直ちに資本欠損が問題化するわけではありません。しかし仮にインフレ加速で量的引締め(QT)に踏み切り、含み損を抱えた国債を売却せざるを得なくなれば巨額の実現損が発生し、財務健全性が損なわれかねません。金利急騰時には日銀の評価損拡大により日銀の債務超過リスクや通貨信用への不安が高まり、金融市場(国債市場・為替市場)にも波及する恐れがあります。
(2) 政府の財政への影響:国債利払い負担の増大
日本政府は普通国債残高が1,000兆円超という巨額の債務を抱えており、金利上昇時には国債の利払い費が急増します。現在、超低金利のおかげで政府の国債利払い費(利息部分)は年約10.5兆円(2025年度当初予算ベース)に抑えられています。しかし金利が2%台に上昇し定着すれば、新発債の利率が上がるにつれて年20兆円規模まで利払い費が増加していく可能性があります。実際、財務省の試算によれば長期金利上昇を織り込んだケースで2028年度の国債利払い費は16.1兆円と、2025年度の10.5兆円から約1.5倍に膨らむ見通しです。これは想定金利がまだ1%台半ばの場合であり、金利2%を超える水準が続けば利払い費は十数兆円規模の上乗せとなり、他の予算を圧迫するのは確実です。金利3%では理論上、利払い費は30兆円近く(現在の約3倍)に跳ね上がり、金利4%では40兆円程度(約4倍)にも達すると試算されます。参考までに、2025年度の政府予算における社会保障関係費は約38.3兆円と見込まれています。仮に金利4%で利払い費が40兆円規模に達すれば、国債の利息支払いだけで社会保障費に匹敵する歳出を要することになり、財政運営上「非常事態」と言える状況です。増加する利払い費はそのまま財政赤字の拡大要因となり、プライマリーバランス改善目標も遠のきます。実際、専門家からは「金利が2~3%に上昇すれば日本の財政持続性は危うい」との指摘も出ています。金利急騰時には政府債務の利払い負担増加により歳出全体の硬直化と財政悪化が避けられず、追加の国債発行(さらなる債務増大)や増税・歳出削減といった困難な調整を迫られるでしょう。
以上のように、2025年2月時点での日銀の国債・株式・ETFの保有状況を見ると、国債には数十兆円規模の含み損が発生し、一方でETF等には同程度の含み益が生じています。金利が2%、3%、4%へと急騰するシナリオでは、日銀保有国債の評価損失が急拡大して日銀のバランスシートは大きく毀損し、同時に政府の国債利払い負担も爆発的に増加して財政悪化は深刻化します。シナリオを単純化した試算ではありますが、具体的な金額規模を示した通り、金利上昇が財政金融に与えるインパクトは極めて大きく、「低金利の長期化」に依存してきた日本経済・財政にとって金利正常化は大きな試練となることが明確です。
毎週1回情報をまとめてお送りします。

AI TRUSTでは日々の金融市場に影響を与えるニュースを独自の視点から解説を行っています。是非ご自身の投資指標としてご活用ください!!